整体って最近できた健康法…そう思っている方も多いかもしれません。
でも実は、整体のルーツはずっと昔、縄文時代や弥生時代にまでさかのぼると言われています。
その起源は1万年以上前にさかのぼるとも考えられています。
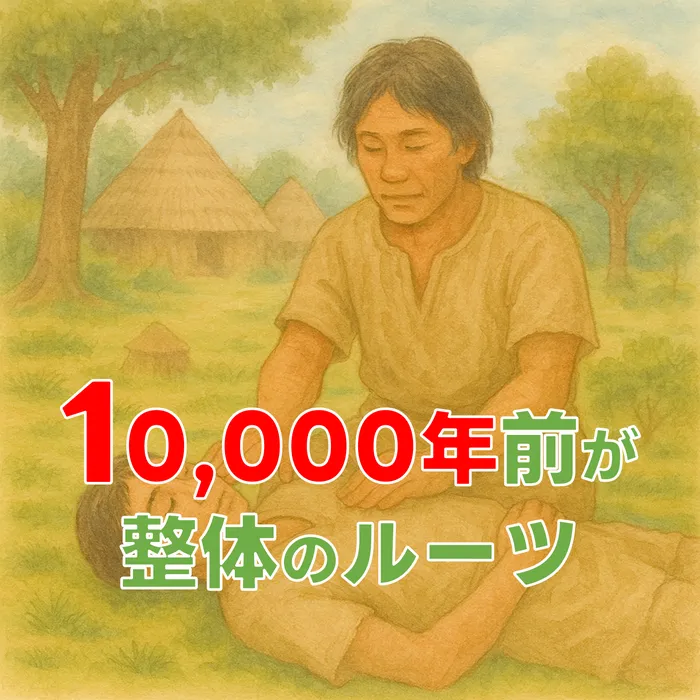
手を当てる――それが整体の原点
もちろん、当時は「整体」なんて名前はなかったでしょう。
でも、人は昔から体の痛みや不調を感じながら生きてきました。
そして、そのたびに…きっと、誰かがそっと手を当てていたのです。
たとえば、どこかが痛いとき、思わず手でさすったり、押さえたりしたことはありませんか?
そう、「手を当てる」って、誰に教わったわけでもないのに、自然とやってしまいますよね。
この“手あて”こそが、整体の原点だとも言われています。
手あては自然な行動だった
たとえば、どこかが痛いとき、思わず手でさすったり、押さえたりしたことはありませんか?
そう、「手を当てる」って、誰に教わったわけでもないのに、自然とやってしまいますよね。
この“手あて”こそが、整体の原点だとも言われています。
縄文時代の遺跡からは、骨の位置を整えた跡がある人骨や、
体のポーズに意味が込められたような土偶も見つかっています。
弥生時代に入ると、農作業などで体を酷使する場面も増えたでしょうから、
おそらく、身近な人たちの間で自然と体をさすったり、押したりする行為があったはずです。
それは、特別な資格や知識を持った人がいたわけではなく、
家族や集落の中で、おばあちゃんが、お母さんが、そっとふれてくれるような、
そんな暮らしの中の癒しだったのだ想像できます。
昔の人の痛みの解釈とは?
現代では「痛み=悪いところがある」「治さなければいけない」という考え方が主流です。
しかし、昔の人は痛みをもっと自然な現象として受け止めていたように思います。
たとえば…
- 狩りや農作業の疲れがたまって「今日は体が重いな」と感じる
- 季節や天候によって節々がうずくことを「寒さのせい」と考える
- 痛みは体が「休め」「動きを変えよ」と教えてくれているサイン
つまり、痛みは“敵”ではなく、生活の一部であり、自然と共にある証でもあったのではないでしょうか。
だからこそ、「抑える」よりも「寄り添う」感覚で、手を当てたり、体を温めたりしていたのだと思います。
よければ、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
→ 体のケアはいつが効果的?スキンケアと同じく時間帯がポイント
技術は進化しても根っこは変わらない
時代が進むにつれ、鍼灸や漢方、そして武道の世界でも体を整えるという発想が発展し、
それが昭和以降には「整体」という名前でひとつの技術体系になっていきます。
とはいえ、どれだけ技術が発展しても、整体の根っこは今も変わっていません。
「人の手で整える」ということ。
これは、どんなに機械やテクノロジーが進んでも真似できない、人間にしかできないやさしさです。
太古から受け継がれる“手のぬくもり”
当院でも、体のバランスや筋肉の調整を大切にしていますが、
その中心には、手のぬくもりがあります。
それは、太古の昔から人が受け継いできた、大切な文化のひとつかもしれません。
整体は、ただ体を整えるだけではありません。
体をとおして、気持ちや呼吸、心の状態にまで影響を与えます。
それはきっと、ふれるという行為が、人の“奥の部分”にまで届くから。
まとめ
今の時代、スピードや効率が重視されがちですが、
ときには立ち止まって、昔の人たちのように「手でふれる」というシンプルな行為に立ち返ってみるのもいいかもしれません。
あなたが整体を受けるその時間は、縄文時代から続く“癒し”の流れに身をゆだねている瞬間。
約4,000年も前から育まれてきた整体という知恵は、今も私たちのそばにあります。
病気を「治す」のではなく、本来の自分のバランスに戻していく。
そんな選択肢があることを、覚えておいてください。
整体をお探しの方へ。
当院では、昔ながらの“手あて”の精神を大切にしながら、今の時代に合った本格派整体を提供しています。
静かな空間で、自分の体と向き合ってみませんか?
当院のHPはこちらです
→https://kyotanabeseitai.com
