江戸時代の整体って、どんなものだったのでしょうか。
前回のブログでは、縄文・弥生時代から始まった整体についてお話しました。
ご覧になられましたか?
→ 縄文・弥生時代から始まった整体
今回はその続きとして、江戸時代の暮らしや武術の中に根づいていた“整える”という知恵を見てみたいと思います。
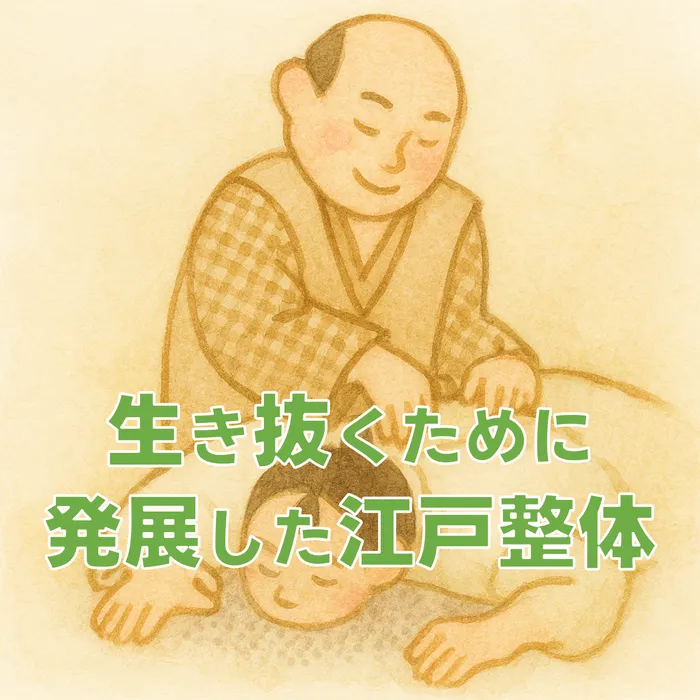
暮らしに根づいた「手あて」
江戸時代は日本独自の文化が花開いた時代。
医学ではオランダからの「蘭方医学」が入り、西洋の知識も広がり始めました。
それでも庶民の間では、腰をさすったり肩をとんとん叩いたりといった「手あて」が日常的に行われていました。
お医者さんにかかれない人も多かった時代、自分の体を守るのは自分たちの手と知恵だったのです。
さらに、近所の年長者や経験者が「この症状にはこうすると良い」と伝える“口伝”も盛んでした。
現代でいうセルフケアやホームケアの原点ともいえるでしょう。
武術における“体を整える”発想
柔術や剣術などの武術の世界では、「戦うための体を作る」ことが重要視されていました。
型や稽古の前後に行われる体ほぐしや調整は、今でいう整体的なケアそのもの。
柔術の師範が弟子の体を整える場面も記録に残っています。
この発想は、現代でいう「体のバランスを整える」ことと同じです。
→ バランスって、じつは奥が深い。
また、武術では「気の流れ」を重視する流派もあり、呼吸や姿勢の調整を通して心身を安定させる方法が受け継がれていました。
修行と導引の広がり
禅の修行や整体法の源流とされる「導引(どういん)」も盛んになった時代です。
導引は、体をゆっくり動かしながら呼吸を整え、気血の巡りを改善する方法。
これは単なるリラクゼーションではなく、生き方を整えるための体へのアプローチだったのかもしれません。
また、寺院や武家屋敷では、健康の維持だけでなく心の安定や集中力向上のためにもこうした鍛錬が行われていました。
現代へのヒント
江戸時代の人々は、病気になってから「治す」よりも、日々の中でバランスを保つことを大切にしていました。
それは食事、体の使い方、人との関わり方まで含めた“生活全体”を整えるという発想です。
当院の整体も、まさにこの考えを引き継いでいます。
不調を取り除くだけでなく、将来のために体を整えておく――
そんな視点を持つことが、これからの健康づくりには欠かせません。
整体は特別な施術ではなく、昔から受け継がれてきた“暮らしの知恵”のひとつです。
あなたも日常に体を労わる時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。
